「量子論はなぜわかりにくいのか」読了 - その1 [読書]
吉田伸夫著、技術評論社「知の扉」シリーズ。
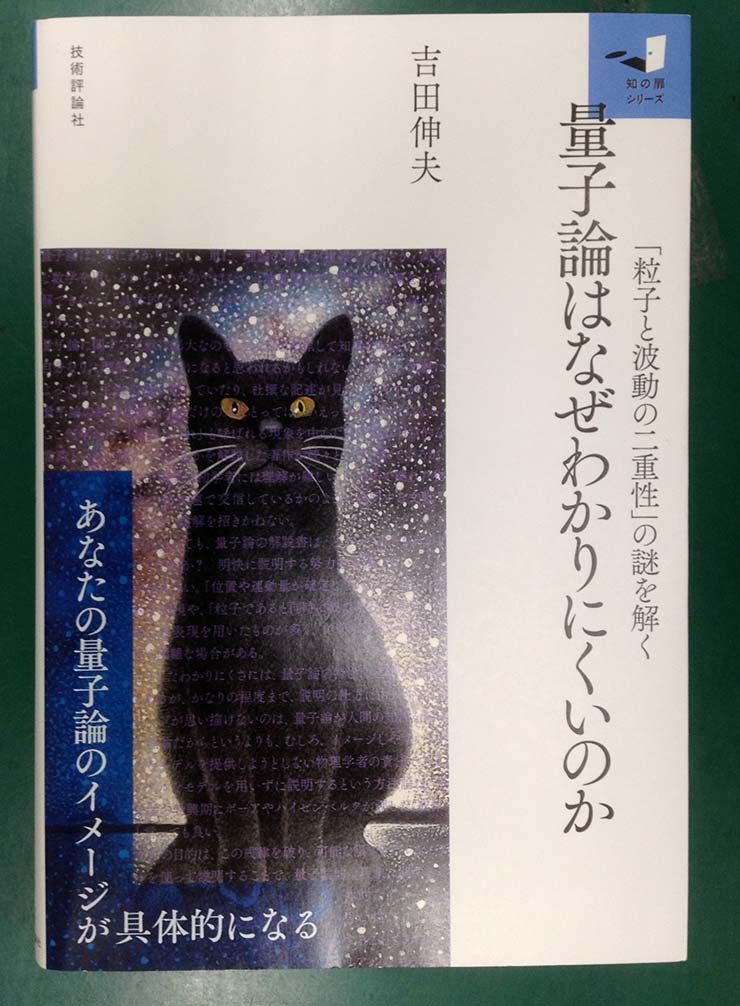 いや、僕にはすごく面白かった。というか膝ポンものの連続だった。でもやっぱり、よくわからないところも残る....
いや、僕にはすごく面白かった。というか膝ポンものの連続だった。でもやっぱり、よくわからないところも残る....
古典力学や電磁気学と同じレベルで量子力学でなければ説明できない現象はいっぱいあるし、古典力学や電磁気学と同じように量子力学を応用した工業製品が作り出されている。つまり量子力学的な現象はそれこそ日常生活にあふれている、のにもかかわらず量子力学に限っては常識に反する局面ばかりが強調されている、もっと直感的に納得しやすい量子力学を提示しよう、というのがこの本の著者の意図である。
この本では最初の方で古典力学の範囲でも「常識に反する」現象はありえるとして逆立ち独楽をあげている。これは摩擦も含めた結構難しい問題で古典力学の応用としては非常に狭い領域になるが、量子力学を説明するときの「波であり粒子である」というような話は、古典論で角運動量を説明するときに逆立ち独楽を例に挙げるようなもので読者を混乱させるだけだというようなことを著者は主張している。
今、僕が仕事で扱っている半導体レーザでは状態密度は量子力学的な計算(とはいえもう決まった計算手順。でも量子ドットなんかを応用したレーザでは計算は大変らしい)をするが、そのあとは劈開端面での共振器としての光密度や端面から出た光の放出は完全にMaxwellの方程式に従う古典的な場として計算する。そういう一連の理論はいわゆる非相対論的でかつ半古典論的な扱いで、正直に言えば統計力学と量子力学と古典電磁気なんかのぐっちゃぐちゃのごった煮に、ダシ取りのための群論が底に沈んでるといった「ベチョたれ雑炊」だけど、まったく矛盾はないどころかそれなりに実験と合う。そこに猫の生き死にに影響するような深遠な問題はまったくでてこないし、それに似たようなことを気にする場面もまったくない。
著者はたびたび量子力学を実用理論であると書いている。僕も量子力学の原理的な問題の存在を知らないわけではないけれど、そもそも半導体物性なんかの基礎理論としてしか理解できていない。確かに僕は学生の頃悩まされた量子力学の難しさをいつの間にか忘れて、例えば電子みたいなフェルミ粒子をなんでかは知らないけど1次元に積み重なるかさばった物だ、としか考えなくなっていた。
今僕のいる会社には、半導体レーザの黎明期に開発者として従事した人が何人かいるけど、彼らも電子が粒子か波かなんて悩んだとは思えない。そういう僕らの態度では量子力学を著者の言う「実用理論」としてしか認識していないと言われても仕方がない。むしろだから著者の主張は僕には「ああ、その通りだ」と素直に、というか至極当然と同意できる。
そして、おお結構面白かった、と読み終わってから気がついたんだけど、僕はひょっとするとこの本の理想的な読者かもしれない、と思った。ここでもときどき書いてきたけど、僕は学生のとき固体物性を専門にして量子力学や解析力学を勉強したが、非相対論的な第2量子化のさわりまでで場の量子論はやらなかった(たしか電磁気学を解析力学的に扱って場のハミルトニアンやラグランジアンの話から、場の量子論につなぐ固体物性の基礎理論みたいな講義が修士の時にあったけど、単位を落とした)。
会社に入ると僕は希望していた物性の技術屋から光ディスクの光学系を扱う光学屋に強制的に転進させられた。扱う話は回折に基づく物理現象が相手で、場としての光の基礎をやりなおすことになった。さらにその中で、ある問題をきっかけにレンズの収差の評価はその使用波長でやらないといけない、という必要性を感じて、当時の赤外の半導体レーザを光源にして干渉計を作り、干渉の現象、コヒーレンシの問題なんかを文字通り身をもって体験した(今の赤や緑のレーザは見えるし、コヒーレンシ高いし干渉計はあのころに比べればずっと簡単だろう。いやそれは愚痴でしかないけど)。
つまり
これはもうこの本は僕のために書かれたか、あるいはこの本のために僕は存在してるのか、というような、鍵の凸凹の形がシリンダの並びにぴったりあった、みたいな話に思えてくる。
僕と似たような経験をしている人は是非読んでみてもらいたい。そこまで同じでなくても学生時代に量子力学に苦しめられた人はいっぱいいるだろう。そう言う人で、古典場に慣れているという人ならきっと膝ポンだろうと思う。
とまあ、このへんまではなんとなく納得がいく。もちろん数学をちゃんと追ったわけではないので雰囲気でしかないけど。
さらに著者はEPR相関とベルの不等式に関して
量子論でベルの限界が破られるのは、現実に起きない過程に確率を割り当てようとした結果、見かけの上で確率の正値性が成り立たないから
だと考えるのが、最もナイーブな解釈だと思われる、と書く。
Bellの不等式も不思議でもなんでもない、そもそもありえない確率を足そうとするから混乱するのである、と言っている。これはなかなか難しい。これに関して僕が何を悩んでいるかを、計算を交えながら説明したい。でもすでにかなり長くなったので次回へ.....
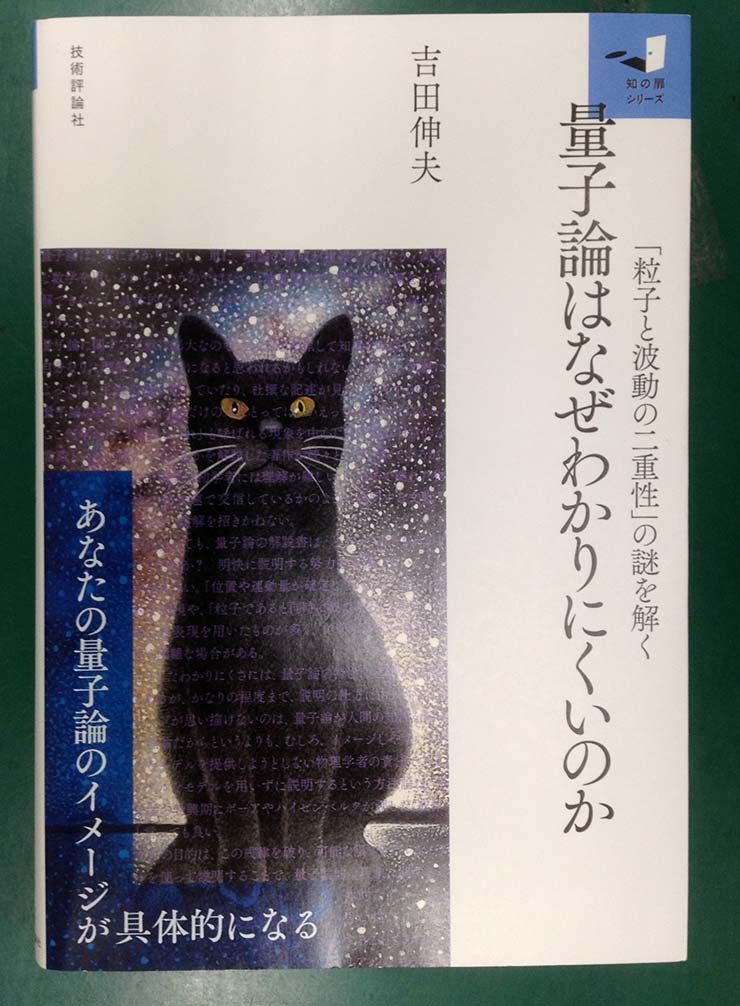
古典力学や電磁気学と同じレベルで量子力学でなければ説明できない現象はいっぱいあるし、古典力学や電磁気学と同じように量子力学を応用した工業製品が作り出されている。つまり量子力学的な現象はそれこそ日常生活にあふれている、のにもかかわらず量子力学に限っては常識に反する局面ばかりが強調されている、もっと直感的に納得しやすい量子力学を提示しよう、というのがこの本の著者の意図である。
この本では最初の方で古典力学の範囲でも「常識に反する」現象はありえるとして逆立ち独楽をあげている。これは摩擦も含めた結構難しい問題で古典力学の応用としては非常に狭い領域になるが、量子力学を説明するときの「波であり粒子である」というような話は、古典論で角運動量を説明するときに逆立ち独楽を例に挙げるようなもので読者を混乱させるだけだというようなことを著者は主張している。
今、僕が仕事で扱っている半導体レーザでは状態密度は量子力学的な計算(とはいえもう決まった計算手順。でも量子ドットなんかを応用したレーザでは計算は大変らしい)をするが、そのあとは劈開端面での共振器としての光密度や端面から出た光の放出は完全にMaxwellの方程式に従う古典的な場として計算する。そういう一連の理論はいわゆる非相対論的でかつ半古典論的な扱いで、正直に言えば統計力学と量子力学と古典電磁気なんかのぐっちゃぐちゃのごった煮に、ダシ取りのための群論が底に沈んでるといった「ベチョたれ雑炊」だけど、まったく矛盾はないどころかそれなりに実験と合う。そこに猫の生き死にに影響するような深遠な問題はまったくでてこないし、それに似たようなことを気にする場面もまったくない。
著者はたびたび量子力学を実用理論であると書いている。僕も量子力学の原理的な問題の存在を知らないわけではないけれど、そもそも半導体物性なんかの基礎理論としてしか理解できていない。確かに僕は学生の頃悩まされた量子力学の難しさをいつの間にか忘れて、例えば電子みたいなフェルミ粒子をなんでかは知らないけど1次元に積み重なるかさばった物だ、としか考えなくなっていた。
今僕のいる会社には、半導体レーザの黎明期に開発者として従事した人が何人かいるけど、彼らも電子が粒子か波かなんて悩んだとは思えない。そういう僕らの態度では量子力学を著者の言う「実用理論」としてしか認識していないと言われても仕方がない。むしろだから著者の主張は僕には「ああ、その通りだ」と素直に、というか至極当然と同意できる。
そして、おお結構面白かった、と読み終わってから気がついたんだけど、僕はひょっとするとこの本の理想的な読者かもしれない、と思った。ここでもときどき書いてきたけど、僕は学生のとき固体物性を専門にして量子力学や解析力学を勉強したが、非相対論的な第2量子化のさわりまでで場の量子論はやらなかった(たしか電磁気学を解析力学的に扱って場のハミルトニアンやラグランジアンの話から、場の量子論につなぐ固体物性の基礎理論みたいな講義が修士の時にあったけど、単位を落とした)。
会社に入ると僕は希望していた物性の技術屋から光ディスクの光学系を扱う光学屋に強制的に転進させられた。扱う話は回折に基づく物理現象が相手で、場としての光の基礎をやりなおすことになった。さらにその中で、ある問題をきっかけにレンズの収差の評価はその使用波長でやらないといけない、という必要性を感じて、当時の赤外の半導体レーザを光源にして干渉計を作り、干渉の現象、コヒーレンシの問題なんかを文字通り身をもって体験した(今の赤や緑のレーザは見えるし、コヒーレンシ高いし干渉計はあのころに比べればずっと簡単だろう。いやそれは愚痴でしかないけど)。
つまり
- 量子力学の基礎的な部分は勉強した
- 古典場の理論として電磁気学は理解している(ただし物質との相互作用は忘れてるところも多い)
- したがって特殊相対論までは理解しているつもり(でも一般相対論は難しい)
- 回折や干渉の現象、さらにはコヒーレンシの問題なんかを実体験として経験している
- 場の量子論は難しくてよくわかっていない
- 量子力学もバンド計算などの手法は知っているが、本当に理解しているかと言うと怪しい
- 従って量子力学の原理的な問題、例えば「波束の収束」とは何かを答えられない
- EPRが何を問題にしているのかよくわかっていない
- ベルの不等式そのものは理解できるが、その意味するところは理解できていない
- 原理的な問題の理解のためにすべてを勉強し直す時間は人生に残されていない
これはもうこの本は僕のために書かれたか、あるいはこの本のために僕は存在してるのか、というような、鍵の凸凹の形がシリンダの並びにぴったりあった、みたいな話に思えてくる。
僕と似たような経験をしている人は是非読んでみてもらいたい。そこまで同じでなくても学生時代に量子力学に苦しめられた人はいっぱいいるだろう。そう言う人で、古典場に慣れているという人ならきっと膝ポンだろうと思う。
1.2 定性的な理解
そうやってこの本や前読んだ本を読んだおかげでちょっとわかったような気がしてきた。僕なりに理解した定性的な内容を書き下してみる。この本での表現と違っているところもあるので、この認識が正しいかどうかは保証の限りではない....1.2.1
時空の性質として色々な場が存在している。それぞれの場は色々な対称性を持った成分からなっている。ミクロにはどの場もラグランジアンの積分を(プランク定数$h$を周期とした)位相として持つ波として場の変化は記述できる。場の変化は経過のすべてを位相も含めて足し合わせることでその変化があり得るかどうかの確率を与える。これが経路積分である。1.2.2
場は位相を持っているため干渉や回折が起こる。干渉が観測にかかるような現象では波として観察されることになる。とくに$\hbar$の大きさが無視できないような現象では場は広がりを持っているように見える。これが量子的な不確定さである。一方で$\hbar$の大きさが無視できるような現象であっても干渉は起こっている。それはただコヒーレンシがなくなった状態(位相が完全にランダムな足し合わせ)になっていると理解できる。そして$\hbar$が0の極限(位相の和の結果がデルタ関数的)で経路積分は最小作用の原理と等価になり、古典論に一致する。1.2.3
ミクロな過程は非常に高速で、人間が観測できるのはたいてい場の定常状態(正確には準定常)である。定常状態とは場が定在波だけになった状態であり、定在波は任意の状態をとることはできず、境界条件で決まる(無限遠で0というのも境界条件の一種である)整数で指定可能な状態だけが実現される(古典論の範囲でも同じような現象がある)。それが量子化である。しかし場そのものはある位置で瞬時的には任意の値を取り得る。1.2.4
ミクロな過渡的変化はあまりに速いため観測は困難で、普通は無視できる。定常状態の間の遷移確率を記述したのがハイゼンベルグの量子力学(行列力学)である。むしろ行列力学は積極的に遷移の過程は記述不能であると主張する。しかしそれは自らの限界に目を瞑るためのストイシズムであると言えなくもない。1.2.5
粒子としての電子は電子の場が量子化され、個数が数えられる(整数で指定される)ようになった状態である。観察可能な原子の内部での電子は定常状態にあるため個数が数えられる状態にあるが、場は原子内部に広がって粒子として孤立してはいない。水素原子での電子場の状態はシュレーディンガー方程式で記述されるのと実質的に等価である。1.2.6
電子を粒子としてみた場合には、全てが誤差なくまったく同じ電荷を持っているのは不思議だが、電子の電荷や質量は数えられる状態にある電子の属性ではなく、重力場における重力定数のような、電子の場の相互作用の結合定数である。従って孤立した電子が同じ電荷を持っているように見えるのはむしろ当然である。1.2.7
また、電子線の回折も単に電子の場の波としての性質が現れただけであって、電子を一個ずつ飛ばしても回折像が現れることに何の不思議もない。2重スリットの実験ではどちらのスリットを通ったか、という設問は意味がなく、電子の場としては両方のスリットの影響を受けた結果である。その意味でラグランジアンの積分に比例した位相を持つ波は実在の波と言っていい。従って「電子は波か粒子か」という問いは、電子の場に対してどんな古典的な描像のアナロジーが可能か、という設問に過ぎず、本質的ではない。1.2.8
一方で散乱のような現象では過渡状態が重要になる。過渡現象を定常状態の和として展開することは可能である。それが摂動展開で、観測可能な(すなわち整数で指定可能な)始状態から同様に観測可能な終状態の間には場のアナログな性質(量子化されず任意の値を取り得る)が現れるため、散乱現象の摂動展開による記述には多くの項が必要になる。とまあ、このへんまではなんとなく納得がいく。もちろん数学をちゃんと追ったわけではないので雰囲気でしかないけど。
さらに著者はEPR相関とベルの不等式に関して
量子論でベルの限界が破られるのは、現実に起きない過程に確率を割り当てようとした結果、見かけの上で確率の正値性が成り立たないから
だと考えるのが、最もナイーブな解釈だと思われる、と書く。
Bellの不等式も不思議でもなんでもない、そもそもありえない確率を足そうとするから混乱するのである、と言っている。これはなかなか難しい。これに関して僕が何を悩んでいるかを、計算を交えながら説明したい。でもすでにかなり長くなったので次回へ.....
2017-05-10 21:02
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)


コメント 0