「六つの航跡」読了 [読書]
ムア・ラファティ著、茂木健訳、創元SF文庫。ここんとここのブログに書けるような本を読んでなかったので久しぶり。
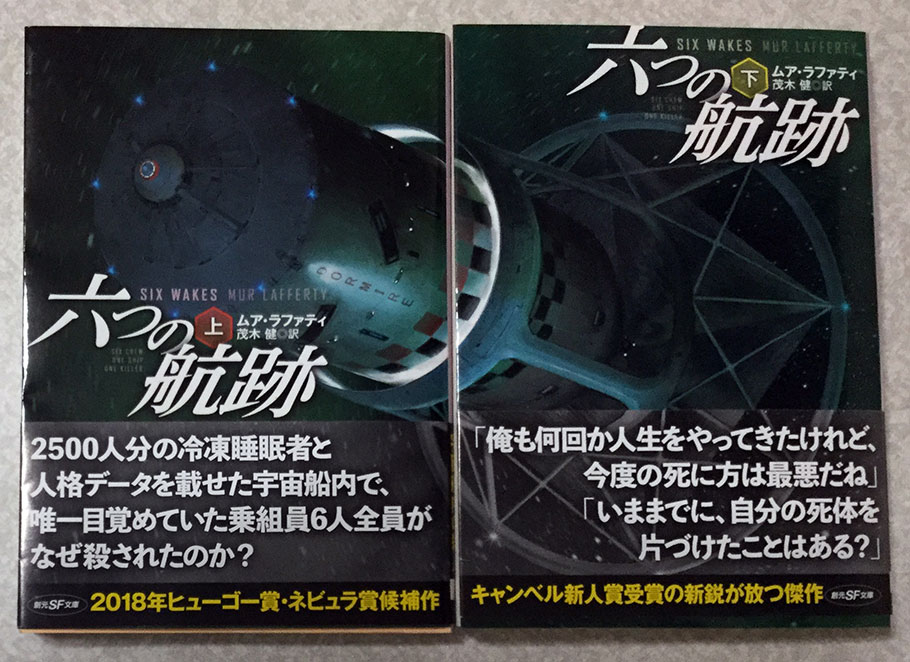
ハードSFかと思って読みだしたら違ってた。でなくてSFミステリなのかな、と思ってずっと読んでった。会話が多くてサクサク読めて、そこそこ面白かったんだけど、最後10ページほどはがっかり....
2千人のコールドスリープ中の人間と、クローンを再生できる「マインドマップ」というデータを5百人分以上積んだ移民船ドルミーレ号(「dormire」はイタリア語で「眠る」という意味らしい。dreamと同じ語源なのかな)は12光年先のアルテミスという惑星に向かっていた。船は活動可能な(眠っていない)六人の乗員と一人のAIによって操船されていたが、乗員の一人であるマリアは自分がクローン再生されて培養タンクにいることに気がついた。さらに彼女は船の人工重力が停止していて、まわりには他の乗員や自分自身の死体が浮かんでいることを知る。他の五人もクローン再生されてくるが、出発後すでに25年間が経っていて、出発直後からの記憶はAIを含めて無くなっており、船はアルテミスへの軌道からはずれつつあることがわかった。乗員たちは何が起こったのか調べ始める....
移民宇宙船はSFにときどきある人間社会に対する仮説とかアンチテーゼではなく、単に閉鎖環境としてSF大道具あるいは舞台を提供しているだけである。物語の中心はそんなところにはなくて、船が出発する200年ほど前に確立した人間のクローンニングの技術と、それによってもたらされた道徳的宗教的な問題、クローンと人間との確執、技術の利用を制限するための法律、またそれをかいくぐるハッカーたちや、さらに彼らを利用しようとする権力者たちが主題であり、そういった地球でのゴタゴタから逃れるために乗り込んだはずだったのに、実際にはそれを引きずったままの乗員たちが描かれる。
マリアを含めて乗員はクローンであり、記憶を継続したまま何回も再生されて200年あまり生きている。そして乗員全員がなんらかの犯罪者で(帳消しを条件に乗員になっている)、再生されてからはお互い疑心暗鬼に囚われて、トゲトゲギスギスした雰囲気のまま物語は進んでいく。船長のカトリーナが特にコワモテに描かれていたりして、読み始めからキャラの区別はつきやすく配慮されている。
ハードSFかと思って読み始めたんだけど、マリアが再生されたとき遠心力を利用した人工重力が停止している、という記述を読んで、あ、これは違うな、と思った。人が内部で生活できるほど巨大な円筒形(具体的なサイズの記述があったように思うけど忘れた)の宇宙船の角運動量は莫大なもので、しかも角運動量保存の法則がある。電源が切れたら止まって、スイッチを入れたら動き出す、などというようなものではまったくない。
また、DNAのデータから一人の成人をいきなり再生することは、よくある設定ではあるけど、そのためにはDNAだけでは情報不足である。DNAは「設計図」などと言われるので、あとは材料があればできるように思われているかもしれないけど、実際にはせいぜい料理の「レシピ」のようなもので、ひとつの独立性の高い「卵細胞」から順を追って発生させないとできあがらないし、DNAの塩基配列にはそのためのデータしか含まれていない(毛細血管が体内をどう走るかや肺胞の配置、指紋や虹彩のパターン、あるいはもっと背の高さなどの情報はDNAにはなく、発生の過程で調停的に決定される。したがってクローンするたびに微妙に違ってくるはずである)。そしてどんな未来になっても存在しない情報から再生はできない。普通はそれを創作という。
物語ではデータさえあれば3Dプリンタで出力するようにして人間だけでなく、植物でも豚でも数時間で再生できるようになっている。その装置はまさしく「プリンタ」と呼ばれている(しかし、例えば心臓がプリントされる前はどうやって血液を循環させるのか、臓器が揃うまで培養タンクが全て肩代わりするとしたら、全部が揃ってせーので起動するのか、脳の自律神経系の機能は臓器がない間どうしてるのか、脳が起動したあとどうやってタンクから臓器制御を引き継ぐのか最後の最後に全神経を切り替えるのか...そう考えると発生ってブートプロセスとしてすごく合理的だな)。
さらに、「マインドマップ」は記憶を含めた人格を構成するデータで、コンピュータをプログラムするようにあとから改変できるように描かれていて、しかも唾液に含まれるDNAからその時点までの記憶を含めて復元できるようになっている。それはなんとなくラマルク説を連想させる描写で、実際のDNAにはそんな情報はなく、また何らかの形で「マインドマップ」がデータ化できたとしても、ぐちゃぐちゃにこんがらがった超巨大な毛糸玉のようなもので、わずかな改変であっても全体に影響して違うぐちゃぐちゃになるだけである。
....なんてハードSFオタクのジジイのこうるさいツッコミはとりあえずおいといたとして、それぞれ無関係だと思われていた六人の乗員全員が、出発する以前にある一人の人物とそれぞれ何らかの関係があり、しかもそれがみんなクローンニングにまつわっていて、それぞれがお互いの人生に影響を与えていたことが物語が進むにつれてわかってきて、これはこのあとどうなるんだろう、と思いながら読み進めた。
でもそのカラクリはかなり大味で、ここに具体的には書けないけど、「オリエント急行殺人事件」や「砂の器」を想像してしまうと肩透かしをくらうことになる。まあ、そんな傑作と比べる方が悪い、とは言えるけど。
クローンの技術によって人間やその社会にどんな影響があるか、というのはSFとしてとしてだけでなく文学として興味深いテーマである。この物語のようにプリンタでほいほい、というわけにはいかないけど、すでに現実に考えないといけない状況にある、と言っていい。この物語では一人の人物の「マインドマップ」とその人のクローン情報(それはこの物語ではすなわち塩基配列のようである)をセットで肉体をクローンすれば、それは同一人物という扱いになっているようである。
そしてその手続きを繰り返せば記憶や自意識を保ったまま壮健な肉体を得ることができて、それはつまり「死」を克服するということである。一方で「個人」として認められるのは最新のマインドマップを持った個体だけで、それ以前の個体は処置されなければならない、という法律があることになっている。人間の完コピが可能になったとき、アイデンティティは大問題であって、それに対する社会的な反応も物語では描かれる。
全く同じ塩基配列に基づく体(脳の配線具合も含めて)に、全く同じ記憶を持つふたりの人物は同一人物なのか?そのとき自意識あるいは自己認識はどうなのか?たとえばマークテストみたいなやりかたではそれぞれ独立した自己意識を持つとしか判断できないはずである。この物語では同一人物の複数のクローンは違法という設定で、つまりそれは暗に意識も含めて同一人物だという著者の認識なんだろう。
でも、クローンを残して自分は死ぬとき「私は死につつある」と意識しながら死んでいくんだろうし、その人の自意識は死によって途絶えるはずであって、残したクローンによって自分が継続するとは感じられないだろう。一方クローンのほうは自分が継続していると思えるだろうけど、それは後から作られたクローンがそう思っているだけで、クローン元の人格とは別物であって、「死につつある」と意識した人がそれによって再生したわけではない。物語ではそのあたりへの突っ込みはなく、楽観的にスルーされていて、僕には違和感が残った(ちなみにたとえば、萩尾望都の「銀の三角」では、主人公マーリーが2回クローンされるが、それは特殊能力を持ったマーリーの責務遂行が目的で、彼の上司によって行われる。クローンたちは同じ能力を持っているが、明らかに別人格として描かれている)。
もちろん、今の技術の延長線上では、30歳の人間のクローンを作るには30年と10ヶ月かかってしまうはず(それは今の宇宙をビッグバンから作らずに今あるまま作る、というのとまったく同じ問題である。もしクローンの促成栽培が可能なら、本人よりも年上のクローンも可能なはずだろう)なので、完コピの問題は出現し得ない。しかし遠い未来には可能になるかもしれない。クラークの第3法則によれば「十分に進歩した技術は、魔法と区別できない」だそうなので。
しかしそうなれば、この物語に描かれたよりももっと奥深い、人間存在の核心をつく問題が立ち現れるはずである。またそういうSFが現時点で書かれることを僕は期待するし、それはSFならではの物語になるはずである。僕としては、そういうテーマは伊藤計劃に突っ込んで欲しかった....
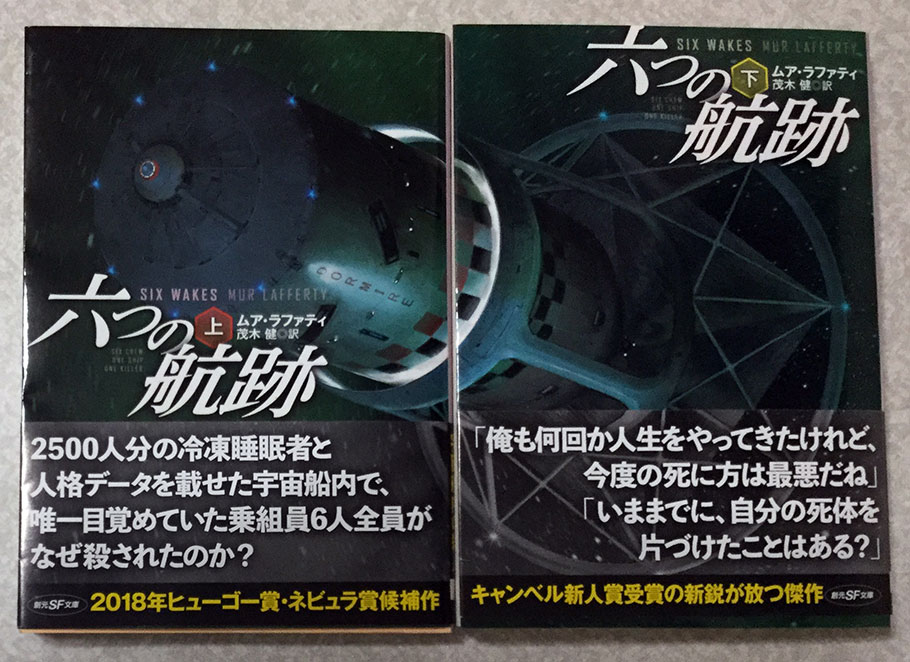
ハードSFかと思って読みだしたら違ってた。でなくてSFミステリなのかな、と思ってずっと読んでった。会話が多くてサクサク読めて、そこそこ面白かったんだけど、最後10ページほどはがっかり....
2千人のコールドスリープ中の人間と、クローンを再生できる「マインドマップ」というデータを5百人分以上積んだ移民船ドルミーレ号(「dormire」はイタリア語で「眠る」という意味らしい。dreamと同じ語源なのかな)は12光年先のアルテミスという惑星に向かっていた。船は活動可能な(眠っていない)六人の乗員と一人のAIによって操船されていたが、乗員の一人であるマリアは自分がクローン再生されて培養タンクにいることに気がついた。さらに彼女は船の人工重力が停止していて、まわりには他の乗員や自分自身の死体が浮かんでいることを知る。他の五人もクローン再生されてくるが、出発後すでに25年間が経っていて、出発直後からの記憶はAIを含めて無くなっており、船はアルテミスへの軌道からはずれつつあることがわかった。乗員たちは何が起こったのか調べ始める....
移民宇宙船はSFにときどきある人間社会に対する仮説とかアンチテーゼではなく、単に閉鎖環境としてSF大道具あるいは舞台を提供しているだけである。物語の中心はそんなところにはなくて、船が出発する200年ほど前に確立した人間のクローンニングの技術と、それによってもたらされた道徳的宗教的な問題、クローンと人間との確執、技術の利用を制限するための法律、またそれをかいくぐるハッカーたちや、さらに彼らを利用しようとする権力者たちが主題であり、そういった地球でのゴタゴタから逃れるために乗り込んだはずだったのに、実際にはそれを引きずったままの乗員たちが描かれる。
マリアを含めて乗員はクローンであり、記憶を継続したまま何回も再生されて200年あまり生きている。そして乗員全員がなんらかの犯罪者で(帳消しを条件に乗員になっている)、再生されてからはお互い疑心暗鬼に囚われて、トゲトゲギスギスした雰囲気のまま物語は進んでいく。船長のカトリーナが特にコワモテに描かれていたりして、読み始めからキャラの区別はつきやすく配慮されている。
ハードSFかと思って読み始めたんだけど、マリアが再生されたとき遠心力を利用した人工重力が停止している、という記述を読んで、あ、これは違うな、と思った。人が内部で生活できるほど巨大な円筒形(具体的なサイズの記述があったように思うけど忘れた)の宇宙船の角運動量は莫大なもので、しかも角運動量保存の法則がある。電源が切れたら止まって、スイッチを入れたら動き出す、などというようなものではまったくない。
また、DNAのデータから一人の成人をいきなり再生することは、よくある設定ではあるけど、そのためにはDNAだけでは情報不足である。DNAは「設計図」などと言われるので、あとは材料があればできるように思われているかもしれないけど、実際にはせいぜい料理の「レシピ」のようなもので、ひとつの独立性の高い「卵細胞」から順を追って発生させないとできあがらないし、DNAの塩基配列にはそのためのデータしか含まれていない(毛細血管が体内をどう走るかや肺胞の配置、指紋や虹彩のパターン、あるいはもっと背の高さなどの情報はDNAにはなく、発生の過程で調停的に決定される。したがってクローンするたびに微妙に違ってくるはずである)。そしてどんな未来になっても存在しない情報から再生はできない。普通はそれを創作という。
物語ではデータさえあれば3Dプリンタで出力するようにして人間だけでなく、植物でも豚でも数時間で再生できるようになっている。その装置はまさしく「プリンタ」と呼ばれている(しかし、例えば心臓がプリントされる前はどうやって血液を循環させるのか、臓器が揃うまで培養タンクが全て肩代わりするとしたら、全部が揃ってせーので起動するのか、脳の自律神経系の機能は臓器がない間どうしてるのか、脳が起動したあとどうやってタンクから臓器制御を引き継ぐのか最後の最後に全神経を切り替えるのか...そう考えると発生ってブートプロセスとしてすごく合理的だな)。
さらに、「マインドマップ」は記憶を含めた人格を構成するデータで、コンピュータをプログラムするようにあとから改変できるように描かれていて、しかも唾液に含まれるDNAからその時点までの記憶を含めて復元できるようになっている。それはなんとなくラマルク説を連想させる描写で、実際のDNAにはそんな情報はなく、また何らかの形で「マインドマップ」がデータ化できたとしても、ぐちゃぐちゃにこんがらがった超巨大な毛糸玉のようなもので、わずかな改変であっても全体に影響して違うぐちゃぐちゃになるだけである。
....なんてハードSFオタクのジジイのこうるさいツッコミはとりあえずおいといたとして、それぞれ無関係だと思われていた六人の乗員全員が、出発する以前にある一人の人物とそれぞれ何らかの関係があり、しかもそれがみんなクローンニングにまつわっていて、それぞれがお互いの人生に影響を与えていたことが物語が進むにつれてわかってきて、これはこのあとどうなるんだろう、と思いながら読み進めた。
でもそのカラクリはかなり大味で、ここに具体的には書けないけど、「オリエント急行殺人事件」や「砂の器」を想像してしまうと肩透かしをくらうことになる。まあ、そんな傑作と比べる方が悪い、とは言えるけど。
クローンの技術によって人間やその社会にどんな影響があるか、というのはSFとしてとしてだけでなく文学として興味深いテーマである。この物語のようにプリンタでほいほい、というわけにはいかないけど、すでに現実に考えないといけない状況にある、と言っていい。この物語では一人の人物の「マインドマップ」とその人のクローン情報(それはこの物語ではすなわち塩基配列のようである)をセットで肉体をクローンすれば、それは同一人物という扱いになっているようである。
そしてその手続きを繰り返せば記憶や自意識を保ったまま壮健な肉体を得ることができて、それはつまり「死」を克服するということである。一方で「個人」として認められるのは最新のマインドマップを持った個体だけで、それ以前の個体は処置されなければならない、という法律があることになっている。人間の完コピが可能になったとき、アイデンティティは大問題であって、それに対する社会的な反応も物語では描かれる。
全く同じ塩基配列に基づく体(脳の配線具合も含めて)に、全く同じ記憶を持つふたりの人物は同一人物なのか?そのとき自意識あるいは自己認識はどうなのか?たとえばマークテストみたいなやりかたではそれぞれ独立した自己意識を持つとしか判断できないはずである。この物語では同一人物の複数のクローンは違法という設定で、つまりそれは暗に意識も含めて同一人物だという著者の認識なんだろう。
でも、クローンを残して自分は死ぬとき「私は死につつある」と意識しながら死んでいくんだろうし、その人の自意識は死によって途絶えるはずであって、残したクローンによって自分が継続するとは感じられないだろう。一方クローンのほうは自分が継続していると思えるだろうけど、それは後から作られたクローンがそう思っているだけで、クローン元の人格とは別物であって、「死につつある」と意識した人がそれによって再生したわけではない。物語ではそのあたりへの突っ込みはなく、楽観的にスルーされていて、僕には違和感が残った(ちなみにたとえば、萩尾望都の「銀の三角」では、主人公マーリーが2回クローンされるが、それは特殊能力を持ったマーリーの責務遂行が目的で、彼の上司によって行われる。クローンたちは同じ能力を持っているが、明らかに別人格として描かれている)。
もちろん、今の技術の延長線上では、30歳の人間のクローンを作るには30年と10ヶ月かかってしまうはず(それは今の宇宙をビッグバンから作らずに今あるまま作る、というのとまったく同じ問題である。もしクローンの促成栽培が可能なら、本人よりも年上のクローンも可能なはずだろう)なので、完コピの問題は出現し得ない。しかし遠い未来には可能になるかもしれない。クラークの第3法則によれば「十分に進歩した技術は、魔法と区別できない」だそうなので。
しかしそうなれば、この物語に描かれたよりももっと奥深い、人間存在の核心をつく問題が立ち現れるはずである。またそういうSFが現時点で書かれることを僕は期待するし、それはSFならではの物語になるはずである。僕としては、そういうテーマは伊藤計劃に突っ込んで欲しかった....
2019-01-20 21:09
nice!(0)
コメント(0)


コメント 0