「ソラリス」読了 [読書]
スタニスワフ・レム著、沼野充義訳、ハヤカワSF文庫。
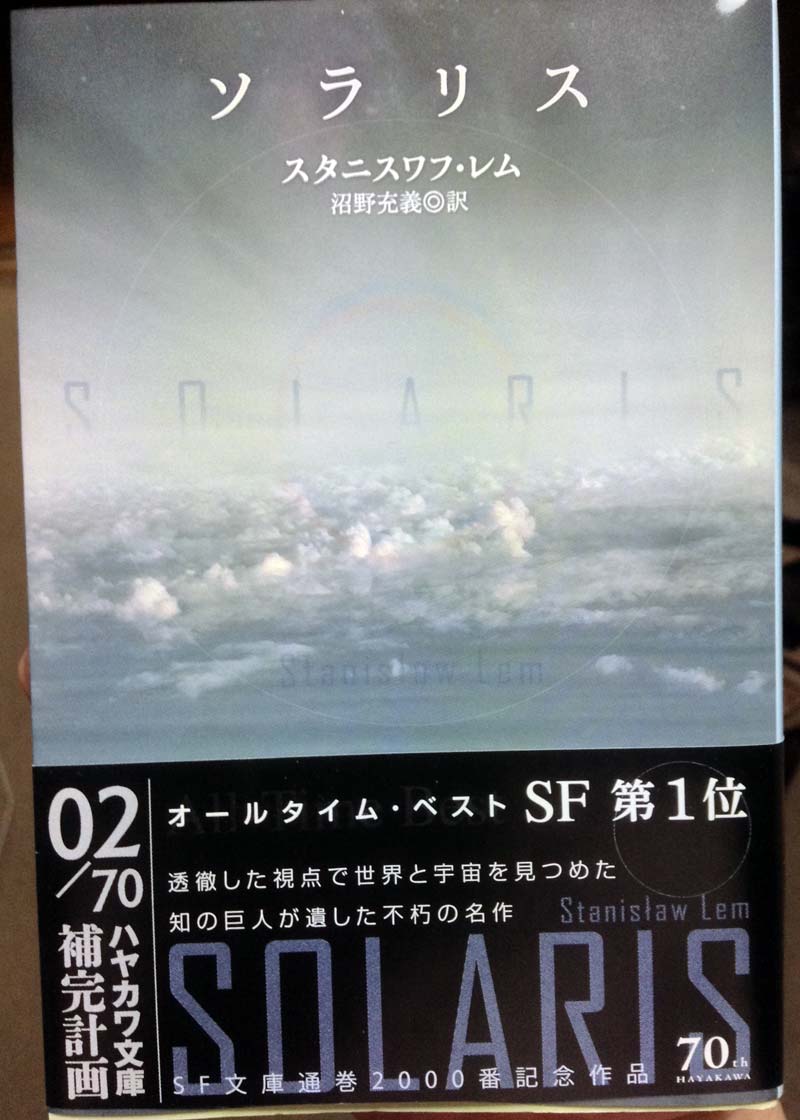
僕は一度、高校生の頃読んだんだけど、これはポーランド語からの新訳(昔読んだのはロシア語からの2重訳だったらしい)というので買って読んだ。レムは大好きな作家で、「ソラリス」は彼の代表作と言われている。40年ぶりに読んで面白かった、と言っていいのかよくわからないけど、「幼年期の終わり」に次ぐ、大好きなSFには違いない。でもクラークと違って、レムを知らない、SFを知らない人に勧めらるかというと難しい...
地球からどのくらい遠いのかよくわからない、ソラリスと呼ばれる惑星。ほとんどが海に覆われている。その上空に浮かぶステーションにケルヴィンというソラリスの研究者がやってくる。彼がステーションに到着したときそこには3人の研究者がいた。しかし知り合いだったギバリャン(ジバニャンではない)は彼が来る直前に自殺していた。
残る二人はなぜか極端によそよそしく、不安定な性格に見える。ケルヴィンは彼らとつかず離れずの距離を置きながらギバリャンが彼に残したメモを読んでステーションの中をうろうろしていると不思議な現象に出会う。研究者のひとりスナウトはそれを「お客さん」と呼んだ。
そのケルヴィンにも突然お客さんが現れる。自分の狭い部屋のベッドで目をさますと、若い女がそばの椅子に座っているのに気づいて、寝起きのぼんやりした頭で言葉を交わす。彼女はハリー。ずっと以前、些細な彼の振る舞いのせいで彼女を自殺に追い込んだ。当然、本物のハリーであるわけはない。その証拠に、彼女が死んでからの友人を知っていると言ったり、彼から離れるのを極端に忌避する(本物の彼女はそうではなかったとケルヴィンは思い出す)。ケルヴィンはハリーをそそのかして連絡用のシャトルロケットに乗せ、衛星軌道に打ち上げる。しかしまもなくハリーはまた彼のそばに現れる....
あらすじを書こうとすると、どうしてもケルヴィンとハリーの話になってしまう。でもそれがこの物語の中心ではない。ケルヴィンのハリー以外にもステーションの研究者にはそれぞれお客さんが来ているらしいことは書かれるが、詳細は不明のままである。ケルヴィンの心理はそれなりに追求されるけど、彼は残った二人の研究者とくらべて人格や行動力や知識や思考力にはそれほど差はなく、結局ほどんと同一人物のように似ている。ハリーも後半では自分の存在を疑って行動を起こすが、若く美しく気まぐれで、物語の中でその内面が掘り起こされることはなく、表層的な存在のまま終わる。
物語の中心はソラリスの海である。お客さんたちは海の能力の表れである。お客さんだけでなく海は、ソラリスが人類に発見されてからずっと研究されてきたいろいろな不思議な現象の原因そのものだった。
ケルヴィンはギバリャンが彼に残したメモにあった本をスナウトから受け取る。それはソラリスに関する初期の資料集で、そこにはベルトンという操縦士がヘリコプターでソラリスの上空を飛んだ日誌と、そのあとのインタビューが収録されていた。
ベルトンはあるとき海に黄色い渦とそれをとりまく霧を発見する。渦から粘液のようなものが伸びてカリフラワーの形の小山になり、それがいろいろな形をなすように見えた。気がつくとそれが木々や小道のある庭の模型のようになった。それから4メートル以上もある人間の子供の形になった、と語る。
ソラリス研究者たちは、そのあと現れる種々雑多な現象を発見し、観察し、分類し、名前をつけた。曰く「山樹」「長物」「ミモイド」「キノコラシキ」「対称体」「非対称体」....人間が見慣れたものとは似ても似つかない形や動きがつぎつぎにいくらでも脈絡なく現れる。しかしなんのために現れるのかはまったくわからなかった。
物語ではケルヴィンがステーションの図書館にある文献をあさり、ソラリス研究の歴史を紐解いていく。異なる現象が観察されるたびに新しい仮説が大量に提出され議論されるが、結局わからないまま放置される。徐々にソラリス研究は衰退していく。
これはときどきレムがやる、歴史の創作である。レムは惑星の文化の歴史や新しい学問分野の歴史を緻密にでっちあげて物語の中で開陳するが、一種のパロディである。読んでいてそれ自身を面白いと思わなければ、なかなかついていくことさえ難しいことがある。「ソラリス学」はその中でも比較的わかりやすい方だとは思うけど、人によってはダラダラしてつまらないと思うかもしれない。
物語の後半では、ケルヴィンは海がハリーをわざわざ生理機能までシミュレートして再現していること(彼は、ハリーの着ている服が脱ぐためにはハサミで切るしかないしろものなのに、ハリーの心臓が鼓動を打つのを見て、さらに顕微鏡を使って彼女の血液にも赤血球があることを知る。しかし、それを実現している物理は人間とは全く違っていることを発見する)に気がつくけど、なぜ何のために海がそんなことをしてまでハリーを彼のもとによこすのかはどうしても理解できない。ケルヴィンは混乱したまま偽物だとわかっているハリーを受け入れ、彼女と離れ難くなっていく。
この「ソラリス」はレムの小説にときどき、というか、かなりよくある「真実は常に明らかになるとは限らない」「すべてが人間に理解可能だとは限らない」というテーマを追求したものである。「ソラリス学」の膨大さとその挫折はまったくそのものだし、海が見せる頭に思い描くのも難しい抽象的な形や動き(レムがああでもないこうでもないとこねくり回したイメージをなんとか伝えようと悪戦苦闘している感じがする)も理解不能性を語っている。
本のなかほどに「ソラリス学」の問題点として「アントロポモルフィズム(人間形態主義)」という言葉が出てくる。もとは宗教に関する言葉らしいけど、人間以外のものに人間の特徴を見出して理解しようとする姿勢のようにレムは書いている。つまりは人間中心主義的(「ゾオモルフィズム(動物形態観)」という言葉も出てくるけど、大きくは同じことである)な理解の仕方、ということらしい。つねにそういう理解の仕方が可能とは限らない、あるいはそれで理解できたと考えるのは危険である、ということをレムは言っているようである。
異質なものは理解できないだろうというような、なんとなく人間の能力を限定するような否定的な主張に感じられるかもしれないけど、安易な理解による思考停止を避け、「すべてわかった」というような態度に陥らないようにしよう、というレムの提案だと僕は思っている。
「ソラリス」では人類はいろいろな惑星を探査しているがソラリスは極端な存在で、他の惑星はソラリスに比べれば理解可能らしい。しかし僕は、今後人類が宇宙に進出して他の太陽系の惑星に降り立ったとき、現実の宇宙では人類はどこへ行ってもまた違ったソラリスに出会うだけなのではないか、と思う(ちなみに、「鯨イルカは知性が高いから人間が食べてはならない」とか「猿にも人権を」なんかはアントロポモルフィズムだと、僕には思える)。
レムはいつもそうだけど、この「ソラリス」でもレムは自分ひとりで考えて自分ひとりで言葉を紡ぎだす。「ソラリス」で語られることはすべてレムの頭の中から出てきたものであることが読んでいて行間から伝わってくる。「ソラリス」を語るというレム自身の姿勢が、アントロポモルフィズムを避け、思考し続けるお手本となっている。
ただ、レムはそのせいで舌足らずだったり、逆にむやみに冗長だったりするとことがあって、「ソラリス」はまだましだけど、他の小説では尻切れとんぼになったりすることがある。でも、僕にとってレムの書く言葉くらい無条件に信用できる、と思える作家はいない。
ハヤカワのこの文庫の商品詳細にはレムのことを「知の巨人」と呼んでいるが、僕はそうは思わない。あえて言うならレムは「思考の巨人」である。あまりに遠いけど僕もこうありたい。
追記:巻末の訳者による解説が労作で「ソラリス」批評のカタログにもなっている。レム自身の言葉も含まれていて面白い。
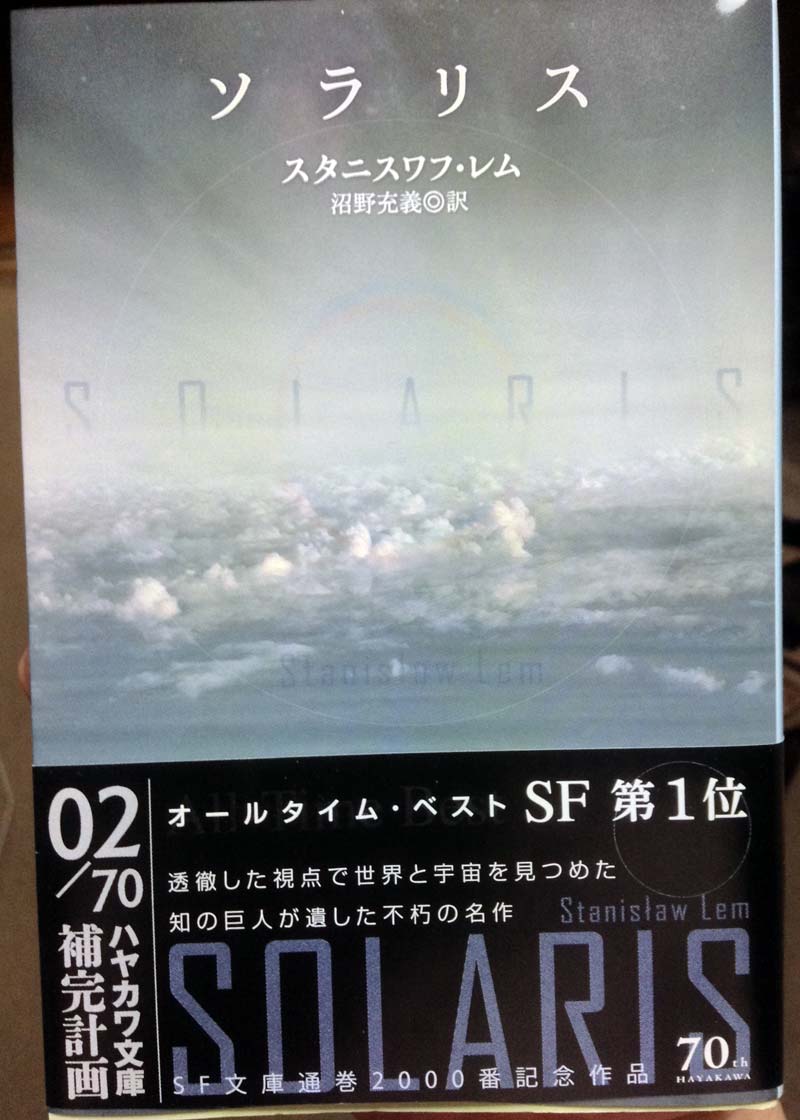
僕は一度、高校生の頃読んだんだけど、これはポーランド語からの新訳(昔読んだのはロシア語からの2重訳だったらしい)というので買って読んだ。レムは大好きな作家で、「ソラリス」は彼の代表作と言われている。40年ぶりに読んで面白かった、と言っていいのかよくわからないけど、「幼年期の終わり」に次ぐ、大好きなSFには違いない。でもクラークと違って、レムを知らない、SFを知らない人に勧めらるかというと難しい...
地球からどのくらい遠いのかよくわからない、ソラリスと呼ばれる惑星。ほとんどが海に覆われている。その上空に浮かぶステーションにケルヴィンというソラリスの研究者がやってくる。彼がステーションに到着したときそこには3人の研究者がいた。しかし知り合いだったギバリャン(ジバニャンではない)は彼が来る直前に自殺していた。
残る二人はなぜか極端によそよそしく、不安定な性格に見える。ケルヴィンは彼らとつかず離れずの距離を置きながらギバリャンが彼に残したメモを読んでステーションの中をうろうろしていると不思議な現象に出会う。研究者のひとりスナウトはそれを「お客さん」と呼んだ。
そのケルヴィンにも突然お客さんが現れる。自分の狭い部屋のベッドで目をさますと、若い女がそばの椅子に座っているのに気づいて、寝起きのぼんやりした頭で言葉を交わす。彼女はハリー。ずっと以前、些細な彼の振る舞いのせいで彼女を自殺に追い込んだ。当然、本物のハリーであるわけはない。その証拠に、彼女が死んでからの友人を知っていると言ったり、彼から離れるのを極端に忌避する(本物の彼女はそうではなかったとケルヴィンは思い出す)。ケルヴィンはハリーをそそのかして連絡用のシャトルロケットに乗せ、衛星軌道に打ち上げる。しかしまもなくハリーはまた彼のそばに現れる....
あらすじを書こうとすると、どうしてもケルヴィンとハリーの話になってしまう。でもそれがこの物語の中心ではない。ケルヴィンのハリー以外にもステーションの研究者にはそれぞれお客さんが来ているらしいことは書かれるが、詳細は不明のままである。ケルヴィンの心理はそれなりに追求されるけど、彼は残った二人の研究者とくらべて人格や行動力や知識や思考力にはそれほど差はなく、結局ほどんと同一人物のように似ている。ハリーも後半では自分の存在を疑って行動を起こすが、若く美しく気まぐれで、物語の中でその内面が掘り起こされることはなく、表層的な存在のまま終わる。
物語の中心はソラリスの海である。お客さんたちは海の能力の表れである。お客さんだけでなく海は、ソラリスが人類に発見されてからずっと研究されてきたいろいろな不思議な現象の原因そのものだった。
ケルヴィンはギバリャンが彼に残したメモにあった本をスナウトから受け取る。それはソラリスに関する初期の資料集で、そこにはベルトンという操縦士がヘリコプターでソラリスの上空を飛んだ日誌と、そのあとのインタビューが収録されていた。
ベルトンはあるとき海に黄色い渦とそれをとりまく霧を発見する。渦から粘液のようなものが伸びてカリフラワーの形の小山になり、それがいろいろな形をなすように見えた。気がつくとそれが木々や小道のある庭の模型のようになった。それから4メートル以上もある人間の子供の形になった、と語る。
....そう、博物館かどこかの人形みたいに見えました。でも、生きているみたいに、口を開けたり閉じたり、あれこれの動作をしたり。いや、ぞっとしました。 ....眼はキラキラ光っていて、生きている子供のような印象を与えました。ただ、体の動きはまるで誰かが試しているというか、試験しているみたいな感じで....
ソラリス研究者たちは、そのあと現れる種々雑多な現象を発見し、観察し、分類し、名前をつけた。曰く「山樹」「長物」「ミモイド」「キノコラシキ」「対称体」「非対称体」....人間が見慣れたものとは似ても似つかない形や動きがつぎつぎにいくらでも脈絡なく現れる。しかしなんのために現れるのかはまったくわからなかった。
物語ではケルヴィンがステーションの図書館にある文献をあさり、ソラリス研究の歴史を紐解いていく。異なる現象が観察されるたびに新しい仮説が大量に提出され議論されるが、結局わからないまま放置される。徐々にソラリス研究は衰退していく。
これはときどきレムがやる、歴史の創作である。レムは惑星の文化の歴史や新しい学問分野の歴史を緻密にでっちあげて物語の中で開陳するが、一種のパロディである。読んでいてそれ自身を面白いと思わなければ、なかなかついていくことさえ難しいことがある。「ソラリス学」はその中でも比較的わかりやすい方だとは思うけど、人によってはダラダラしてつまらないと思うかもしれない。
物語の後半では、ケルヴィンは海がハリーをわざわざ生理機能までシミュレートして再現していること(彼は、ハリーの着ている服が脱ぐためにはハサミで切るしかないしろものなのに、ハリーの心臓が鼓動を打つのを見て、さらに顕微鏡を使って彼女の血液にも赤血球があることを知る。しかし、それを実現している物理は人間とは全く違っていることを発見する)に気がつくけど、なぜ何のために海がそんなことをしてまでハリーを彼のもとによこすのかはどうしても理解できない。ケルヴィンは混乱したまま偽物だとわかっているハリーを受け入れ、彼女と離れ難くなっていく。
この「ソラリス」はレムの小説にときどき、というか、かなりよくある「真実は常に明らかになるとは限らない」「すべてが人間に理解可能だとは限らない」というテーマを追求したものである。「ソラリス学」の膨大さとその挫折はまったくそのものだし、海が見せる頭に思い描くのも難しい抽象的な形や動き(レムがああでもないこうでもないとこねくり回したイメージをなんとか伝えようと悪戦苦闘している感じがする)も理解不能性を語っている。
本のなかほどに「ソラリス学」の問題点として「アントロポモルフィズム(人間形態主義)」という言葉が出てくる。もとは宗教に関する言葉らしいけど、人間以外のものに人間の特徴を見出して理解しようとする姿勢のようにレムは書いている。つまりは人間中心主義的(「ゾオモルフィズム(動物形態観)」という言葉も出てくるけど、大きくは同じことである)な理解の仕方、ということらしい。つねにそういう理解の仕方が可能とは限らない、あるいはそれで理解できたと考えるのは危険である、ということをレムは言っているようである。
異質なものは理解できないだろうというような、なんとなく人間の能力を限定するような否定的な主張に感じられるかもしれないけど、安易な理解による思考停止を避け、「すべてわかった」というような態度に陥らないようにしよう、というレムの提案だと僕は思っている。
「ソラリス」では人類はいろいろな惑星を探査しているがソラリスは極端な存在で、他の惑星はソラリスに比べれば理解可能らしい。しかし僕は、今後人類が宇宙に進出して他の太陽系の惑星に降り立ったとき、現実の宇宙では人類はどこへ行ってもまた違ったソラリスに出会うだけなのではないか、と思う(ちなみに、「鯨イルカは知性が高いから人間が食べてはならない」とか「猿にも人権を」なんかはアントロポモルフィズムだと、僕には思える)。
レムはいつもそうだけど、この「ソラリス」でもレムは自分ひとりで考えて自分ひとりで言葉を紡ぎだす。「ソラリス」で語られることはすべてレムの頭の中から出てきたものであることが読んでいて行間から伝わってくる。「ソラリス」を語るというレム自身の姿勢が、アントロポモルフィズムを避け、思考し続けるお手本となっている。
ただ、レムはそのせいで舌足らずだったり、逆にむやみに冗長だったりするとことがあって、「ソラリス」はまだましだけど、他の小説では尻切れとんぼになったりすることがある。でも、僕にとってレムの書く言葉くらい無条件に信用できる、と思える作家はいない。
ハヤカワのこの文庫の商品詳細にはレムのことを「知の巨人」と呼んでいるが、僕はそうは思わない。あえて言うならレムは「思考の巨人」である。あまりに遠いけど僕もこうありたい。
追記:巻末の訳者による解説が労作で「ソラリス」批評のカタログにもなっている。レム自身の言葉も含まれていて面白い。
2015-04-28 22:36
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)


コメント 0